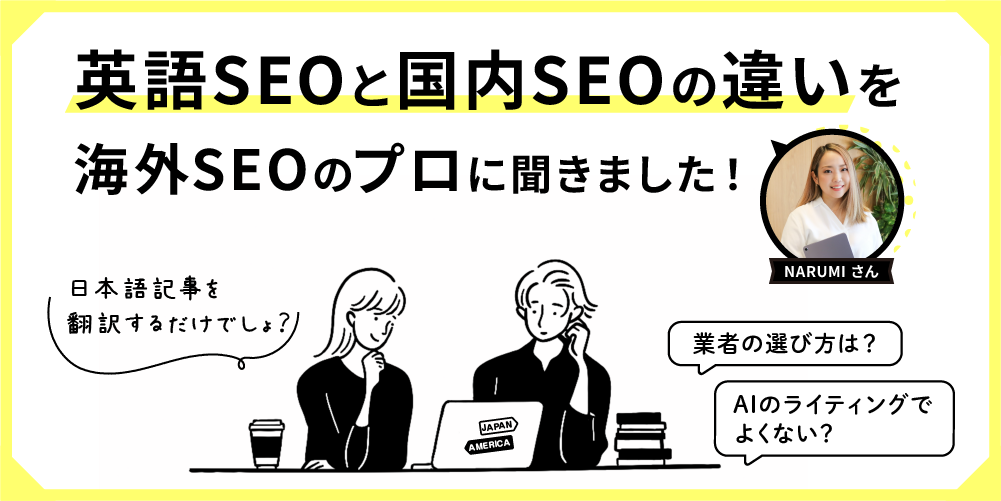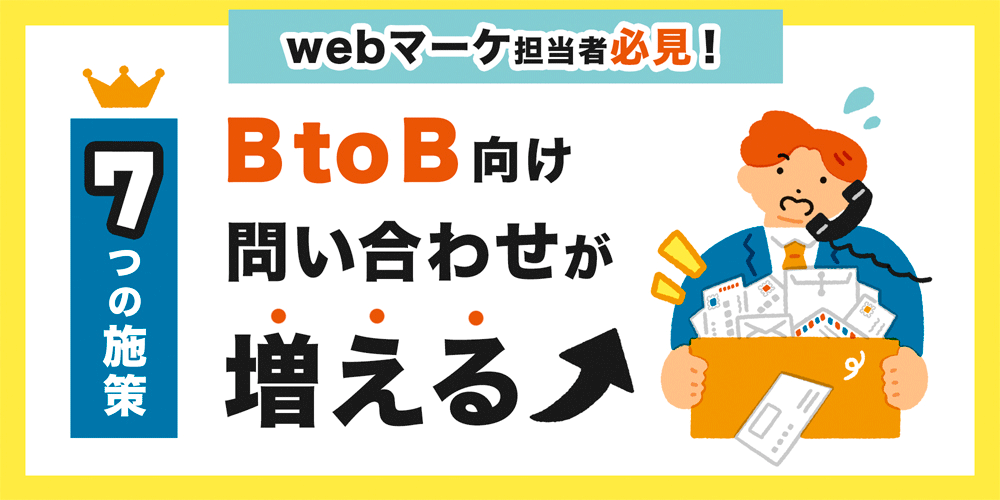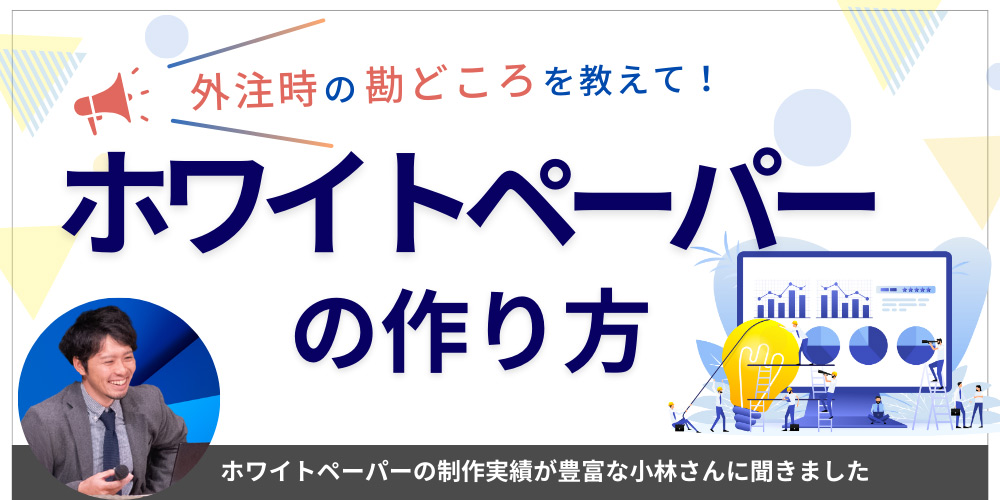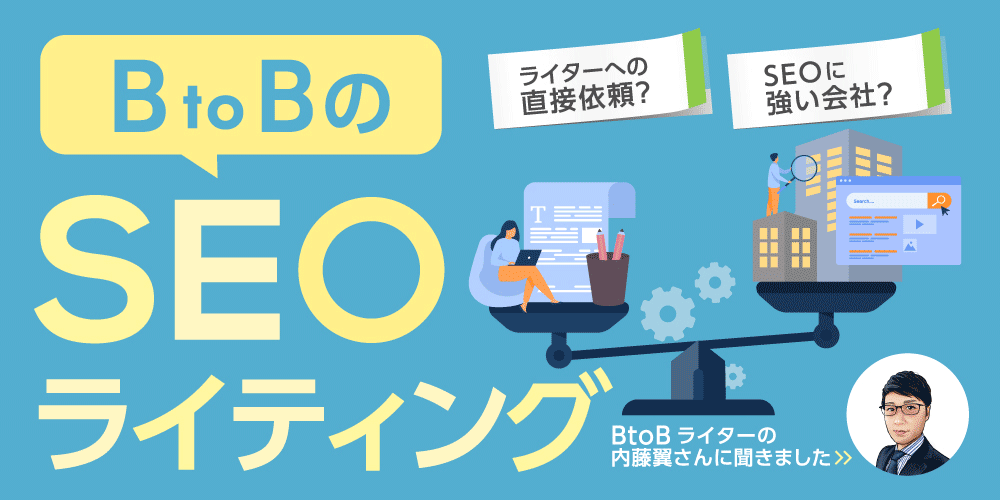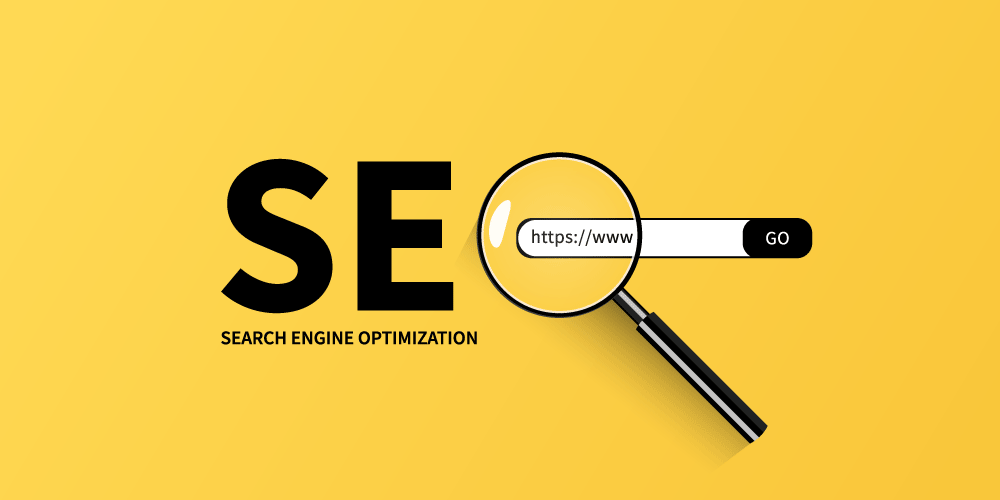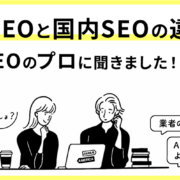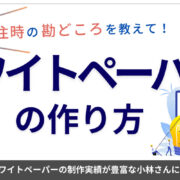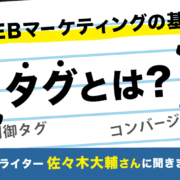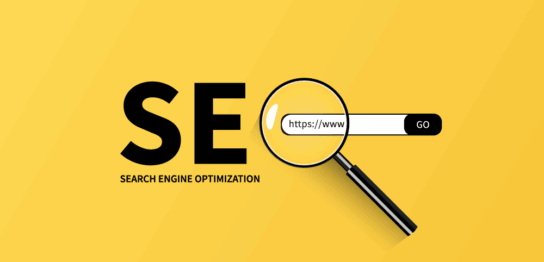さまざまなBtoBコンテンツ制作に携わってきた筆者が、自社の問い合わせを増やすためのノウハウを解説します。幅広いBtoB業界のどの領域にも役立つ内容です。
BtoBマーケティングにおいて、問い合わせの増加は売上向上の重要な指標です。しかし、BtoCと異なりBtoBの購買プロセスは複雑で担当者も複数に渡るため、なかなか成果が出にくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、BtoB企業が問い合わせを増やすために、取り組みやすい7つの施策を厳選して紹介します。SEO対策やコンテンツマーケティング、Web広告などそれぞれの施策の具体的な方法を解説しますので、ぜひ自社のWeb戦略に取り入れて問い合わせ数アップを実現してください。
「ミニマリストの片付け」を運用するトレファクテクノロジーズが、広範なBtoBライターネットワークを活かし、専門性の高い各種コピーライティング、メディアを活用した記事広告施策など、ご要望に最適なライティング施策やSEOコンサルティングをご提供いたします。
BtoB企業が問い合わせを増やす7つの施策

問い合わせを増やすためには、顧客の購買プロセスに合わせたコンテンツづくりが重要です。ここでは、問い合わせを増やす効果的な施策を7つ紹介します。
施策① SEO対策を徹底する
既存のSEO記事があるにも関わらず、KW検索からの流入が少ない場合はSEO対策を見直します。
まずは、ターゲット顧客が実際に検索するKWと、コンテンツで使用しているKWにズレがないか確認します。ニッチ過ぎたり競合が多過ぎたりするKWを選んでいる場合は、ニーズがあり競合の少ないKWを選び直しましょう。タイトル・見出しにKWを盛り込めば、検索エンジンにアピールしやすくなります。
コンテンツの内容が薄く、ユーザーの疑問に答えられていないなら質の高いオリジナルの情報を加えます。E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ作りが重要です。
サイト構造の問題として、ページが重い、スマホで読みにくい、サイト内リンクが少ないという場合があります。その際は、サイトの軽量化やスマホ対応、内部リンクの追加を行いましょう。内部リンクを増やすことで、検索エンジンがサイト内を巡回しやすくなります。
SEO対策を徹底することで、検索エンジンからの評価が高まりWebサイトへのアクセス数が増加します。これによって、問い合わせや見込み客の増加につながるでしょう。
施策② お役立ちコンテンツにも注力する
問い合わせを増やすためには、ターゲット顧客の課題解決に役立つ情報の提供が不可欠です。顧客ニーズに合わせた高品質なコンテンツは、見込み客の獲得と育成に大きく貢献します。
主なコンテンツと活用方法を以下に紹介します。
- メルマガ
- ホワイトペーパー
- 動画
メルマガは、 定期的に顧客ニーズに合わせた情報を配信することで、継続的な関係性を構築し、見込み客の育成(ナーチャリング)に繋げます。 最新の業界動向や役立つノウハウ、イベント情報などを配信するとよいでしょう。
ホワイトペーパーは、 顧客の課題解決に役立つ専門的な知識や独自の調査結果などを盛り込むことで、コンテンツの有益性と信頼性を高められます。特にIT業界や製造業では、高度な技術を理解してもらうために、技術情報や導入事例がおすすめです。
動画は、製品・サービスのデモンストレーションやインタビューなどテキストだけでは伝わりにくい情報を、直感的に理解してもらうのに効果的です。 YouTubeなどの動画プラットフォームを活用することで、幅広い層へのリーチも期待できます。
施策③ 問い合わせフォームを最適化する
問い合わせフォームの使いやすさは、問い合わせ数に直結します。読みにくさや使いにくさは離脱率を高めるため、定期的な見直しと改善が必要です。
問い合わせフォームの最適化には以下の3つが効果的です。
- 入力項目の絞り込み
- 入力サポートの充実
- スマートフォン対応
必要最小限の項目(連絡先、会社名、部署名、名前など)に絞り込み、入力の手間を減らします。項目を増やすほど営業活動はしやすくなりますが、離脱率も高まるためバランスを考慮します。
入力サポートも重要です。必須項目と任意項目の明確な表示や、入力不備による離脱を防ぐためにエラーメッセージを表示します。郵便番号から住所を自動入力するなど、入力しやすい設計にしてください。
スマートフォンからでも、ストレスなく入力できるデザインにします。古いフォームで表示が崩れている場合は、サイト表示を調整しましょう。
施策④ Web広告で即効性を狙う
Web広告は、短期間で成果を求める際に有効な手段です。
BtoBで特におすすめの広告は以下の通りです。
- リスティング広告
- ディスプレイ広告
リスティング広告は、Googleなどの検索エンジンで特定のKWを検索したユーザーに広告を表示します。購買意欲の高い層へピンポイントに訴求できるため、問い合わせにつながりやすいのが特徴です。KW選定が重要で、製品・サービス関連だけでなく、顧客の課題に関するKWも積極的に活用しましょう。
ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリなどさまざまな場所に、画像や動画で表示します。潜在顧客に視覚的にアプローチし、まだニーズが明確化されていない層への認知度向上に貢献します。運用で特に重要なのが、業界、役職、興味関心といった詳細なターゲティングです。これによって、広告を本当に必要とする可能性の高い層へ効率的に届けられます。
さらに、リターゲティング広告を活用すれば、一度自社サイトに訪れたものの、まだ問い合わせに至っていないユーザーに配信できます。自社の製品・サービスを思い出させ検討を後押しできる効果的な手法です。
施策⑤ SNSでブランド認知度を上げる
SNSは顧客との良好な関係を築き、ブランド認知度を高めるための有効な手段です。単なる情報発信に留まらず、以下を意識して問い合わせ増加を目指します。
- プラットフォームの選択
- コンテンツ戦略
- エンゲージメントの促進
FacebookやX(旧Twitter)、LINE、InstagramなどのSNSプラットフォームはターゲット顧客層に合ったものを選びます。例えばXは、最新情報や業界ニュース、イベント告知など速報性の高い発信に、Facebookは企業文化や事例紹介など親近感を与えるコンテンツの発信に向いています。
コンテンツ戦略では、ターゲット顧客のニーズを明確化して課題解決や事例紹介など価値ある情報を提供します。ユーザーが短時間でチェックできるように、簡潔でわかりやすい表現や視覚的な訴求、行動喚起を意識しましょう。
エンゲージメントを促進するために、コメントや質問への迅速な返信や、ユーザー投稿のリポスト、キャンペーンの実施などで関係性を築きます。
施策⑥ チャットボットで問い合わせのハードルを下げる
問い合わせの増加には、顧客が気軽に質問できる環境づくりが重要です。そこで役立つのがチャットボット。24時間365日、顧客対応を効率化し潜在顧客との接点を増やします。
チャットボット活用のメリットは以下の通りです。
- 顧客対応の効率化
- 問い合わせのハードル低下
- 24時間365日対応
- リード獲得
FAQ(よくある質問)の自動応答化や資料請求の受付、担当者の振り分けなどによって業務が効率化でき、担当者はより高度な業務に集中できます。
チャットボットなら電話やメールよりも気軽に質問できるため「ちょっと聞きたい」顧客層を取り込めます。また、24時間365日対応のため問い合わせの機会損失を防げます。
顧客属性や興味関心などの情報を収集し、ターゲティングの精度向上に活用できるのもメリットです。
以下に導入のポイントを説明します。
- FAQの充実
- 自然な対話
- 有人対応へのスムーズな連携
- データ分析と継続的な改善
よくある質問と回答を網羅的に準備し、チャットボットの回答精度を高めることが重要です。その際、チャットボットを人間らしい自然な言葉遣いにすることで、親近感を与えられます。
チャットボットで対応できない場合は、スムーズに担当者へ引き継げるように有人対応への切り替え機能を設けましょう。
チャットボットの利用状況や顧客のフィードバッグを定期的に分析し、回答内容やシナリオを改善します。
施策⑦ ウェビナーやオンラインイベントで関係性を深める
ウェビナーやオンラインイベントは、潜在顧客との接点を効率的に増やし、関係性を深めるために活用できます。専門知識を共有し、見込み客とのエンゲージメントを高めることで問い合わせ増加に貢献します。
ウェビナー/オンラインイベントが効果的な理由は以下の通りです。
- 専門性の訴求
- 顧客との接点創出
- リーチの拡大
業界の専門家を招き、質の高い情報を提供することで競合との差別化を図り、信頼を獲得できます。
質疑応答を通じて顧客の課題を理解し、ニーズに合わせたソリューションの提案が可能です。
オンライン開催のため、地理的な制約がなく広範囲な潜在顧客にアプローチできます。
ウェビナー/オンラインイベント成功のための3つのポイントを紹介します。
- 質の高い情報提供
- インタラクティブな要素
- アーカイブ配信の活用
製品情報だけでなく、業界トレンド、最新技術、成功事例など顧客の課題解決に役立つ情報に焦点を当てましょう。
参加者との双方向コミュニケーションを促進するために、質疑応答やアンケート、投票などを活用します。
アーカイブ配信することで、リアルタイムに参加できなかった層へも情報を提供し、イベント後も継続的なリード獲得・育成を図ります。
BtoBの問い合わせを増やすために重要なポイント

前述した7つの施策に共通するポイントを紹介します。
ターゲット顧客を明確化する
問い合わせを増やすには「誰に何をなぜ伝えるのか」の明確な定義が重要です。ターゲット顧客を明確にすれば、メッセージの訴求性が高まるため、ピンポイントでアプローチできます。
設定の一例は以下の通りです。
- 誰に:業界、企業の規模、役職など詳細に設定
- 何を:ターゲット顧客の課題を解決できる自社製品・サービスの価値を定義
- なぜ伝えるのか:問い合わせによって顧客にどのようなメリットがあるのかを具体的に提示
まずは、自社の顧客データを分析し、理想的な顧客像を描き出すことから始めましょう。
パーソナライズされた顧客体験を提供する
昨今の顧客は情報過多な状況のなかで、より自分に合った厳選された情報を求めています。BtoBにおいても「パーソナライズされた顧客体験」が重視されます。
顧客データとAIを活用し、Webサイトやコンテンツなどあらゆる接点で顧客のニーズや課題にあわせた情報を提供しましょう。例えば、業界や役職に合わせて異なる情報を表示したり、過去の行動履歴に基づいて最適なコンテンツをレコメンドしたりします。
単なる情報提供だけでなく、インタラクティブな体験の提供も重要です。顧客の疑問に答えるチャットボットの設置や、個別の課題に寄り添う相談会の開催などによって顧客との接点を強化できます。
これらによって、顧客エンゲージメントを高め、信頼関係を構築し、より深い関係性から問い合わせにつなげることが期待できます。
カスタマージャーニーを理解する
顧客はいきなり製品・サービスの購入を検討するわけではありません。情報収集や比較検討、意思決定といった段階を経て初めて問い合わせに至り、最終的には顧客ロイヤリティにつながることもあります。この一連の流れをカスタマージャーニーと呼びます。
カスタマージャーニーは一般的に以下の段階にわけられます。
- 認識: 製品・サービスを初めて知る
- 検討: 情報を集め、比較検討する
- 維持: 購入・利用し、継続利用を検討する
- 支持: 製品・サービスに満足し、周囲に推奨する
カスタマージャーニーを理解することで、顧客のニーズに合わせた最適なコンテンツ戦略を立案し、効果的なマーケティング施策を展開できます。
効果測定と改善を繰り返す
マーケティング施策で重要なのは、効果測定を行い継続的に改善を繰り返すことです。
アクセス数やコンバージョン率、CPA(顧客獲得単価)など重要なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に測定して費用対効果を把握します。MAツールなどの分析ツールを活用し、データから顧客行動を深く理解します。また、A/Bテストなどを実施し、効果的なコンテンツやメッセージを特定することも欠かせません。
効果測定の結果に基づき、Webサイトの改善やコンテンツ修正、ターゲティングの見直しなど改善策を実行します。これらのステップをPDCAサイクル(Plan、Do、Check、 Act)として継続的に回すことで、マーケティング施策の効果を最大化し、問い合わせの増加につなげることができるでしょう。
営業部門との連携を図る
マーケティング部門が獲得した見込み客を、営業部門が効果的にフォローアップすることで、問い合わせからの成約率を高められます。
営業部門は、マーケティング部門から提供された顧客情報を活用し、パーソナライズされたアプローチを行います。両部門は定期的に情報交換を行い、顧客の状況やニーズを共有し、連携強化を図ることが重要です。
マーケティング部門でよく使われるMA(マーケティングオートメーション)ツールと営業部門のSFA(営業支援システム)ツールを連携すれば顧客情報を一元管理でき、スムーズな引き継ぎが可能になります。
ライターの私がSEOやコンテンツマーケティングを推す理由
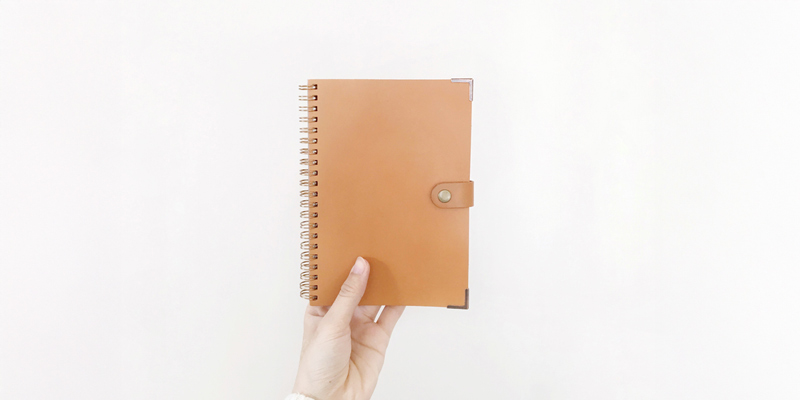
BtoBにおいてもSEOやコンテンツマーケティングは、集客や見込み客の獲得・育成、継続的な売上向上、高い費用対効果などさまざまな効果をもたらします。
ここでは、BtoB領域でSEO記事を執筆してきた経験から、私がSEOとコンテンツマーケティングを推奨する理由を解説します。
推す理由① SEOで信頼構築できる
BtoB顧客は、製品・サービスの比較検討においてWebサイトを最も参考にしています。(トライベック・ブランド戦略研究所「BtoBサイト調査 2024」)
また、課題解決のために検索エンジンで情報を集めている企業に対し、自社のWebサイトが上位表示されていれば「専門的で信頼できる」と認識される可能性が高いといえます。
SEO対策は、単なる順位上げのテクニックではありません。検索エンジンのアルゴリズムを理解し、ユーザーの求める情報を的確に提供することで、Googleから「価値ある情報源」として認められます。
検索結果で上位表示されることは、自社が業界の専門家として認知されるための強力な証となり、問い合わせ増加につながるでしょう。
推す理由② 質の高いコンテンツで引き寄せる
BtoB顧客は、自ら情報収集・比較検討したうえでコンタクトを取る傾向があるため、顧客の購買プロセスに合わせたコンテンツが重要になります。
例えば、以下のようなコンテンツが有効です。
- 課題解決に役立つ記事
- 無料DLできるホワイトペーパー
- 専門家による解説動画
前述したカスタマージャーニーに基づき、顧客が課題に気づいていない「認知」段階ではSEO記事で幅広くアプローチします。解決策を探している「検討」段階では、ホワイトペーパーを用いて導入事例や比較表を配布するなど、顧客の状況に合わせた情報提供が効果的です。
高品質かつニーズに合ったコンテンツは、見込み客にとって有益な情報源となり、自社サイトへの強力な集客を可能にします。コンテンツを通じて信頼関係を築くことで、問い合わせ数や購買意欲を高められるでしょう。
推す理由③ 費用対効果が高い
SEOとコンテンツマーケティングは、短期的な施策ではありません。効果が出るまでには時間と労力がかかりますが、一度軌道に乗れば継続的にリードを獲得できる持続可能な施策です。
広告のように予算を投下し続けなくても、良質なコンテンツは長期に渡り検索エンジンに評価され、リードを生み出し続けます。そのため、中長期的な視点で見ると、非常に費用対効果の高い投資といえるでしょう。
【まとめ】BtoBの問い合わせを増やす施策を行おう
この記事では、BtoB企業が問い合わせを増やすための施策を紹介しました。
集客を強化したいならSEO対策が効果的です。顧客のニーズに合ったKW選定や専門性の高いオリジナルの情報を盛り込むことで、アクセス増加が見込めるでしょう。
また、見込み客の育成にはホワイトペーパー、購入段階では個別見積もりなど、顧客の購買プロセスに応じた施策を展開することが重要です。
紹介した内容を参考に、ぜひ自社に最適な施策を実践し、問い合わせ増加を実現してください。
※こちらの記事の内容は原稿作成時のものです。
最新の情報と一部異なる場合がありますのでご了承ください。
この記事を書いた人
マーケティング系の用語解説をメインにBtoBジャンルでも多様な実績があるライター。リサーチが得意で読みやすい文章を心がけています。